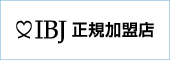ウェルネスメイト東京
夫婦生活コラム(育児編)
寝かしつける

寝かしつけで悩む親は多い
赤ちゃんの寝かしつけは、多くの親にとって試練の一つです。よく眠る子もいれば、全然眠らない子もいます。
ある日、友人の一人が私にこんな話をしてくれました。私の子は、昼間は元気に遊び回り、夜になると急に眠くなってぐずるタイプです。しかし、ベッドに連れて行き、子守唄を歌ってようやく眠りに入ると、そっとお布団に寝かせた瞬間、目をパッチリ開けてしまうのです。「また最初からやり直し…」とため息をつく、そんな気持ちは、多くの親が共感できることでしょう。
赤ちゃんがリラックスできる環境を整える
私自身も、赤ちゃんを抱っこして揺らしながら寝かしつけることがよくありますが、スマホをいじりながらだと、どうしても集中力が欠けてしまいます。その結果、赤ちゃんは敏感にそれを察知し、余計に寝付きが悪くなることが多いです。寝かしつける際の一番のポイントは、赤ちゃんが安心してリラックスできる環境を整えることです。
寝かしつけのルーチンを作る
まず、寝かしつけのルーチンを作ることが大切です。毎晩同じ時間にお風呂に入れ、静かな環境で絵本を読んであげるなど、一定の流れを作ることで、赤ちゃんは「もうすぐ寝る時間だ」と理解するようになります。特に、寝室の照明を暗くし、静かな音楽を流すことで、リラックスした雰囲気を作り出すことができます。
親自身もリラックスする
次に、親自身がリラックスすることも重要です。親のストレスやイライラは赤ちゃんに伝わりやすいです。例えば、一日の終わりにリラックスするための自分自身のルーチンを作り、赤ちゃんと一緒に落ち着いた時間を過ごすことが効果的です。深呼吸をする、お茶を飲むなど、短時間でできるリラックス法を取り入れると良いでしょう。
赤ちゃんが寝入りやすい環境を整える
また、赤ちゃんが眠りに入りやすい環境を整えることも大事です。寝室の温度や湿度を適切に保ち、快適な寝具を選ぶことも、赤ちゃんが安心して眠るためには欠かせません。例えば、適度な厚さの布団や通気性の良いパジャマを選ぶことで、赤ちゃんの睡眠の質を向上させることができます。
赤ちゃんの体内時計を整える
そして、赤ちゃんの体内時計を整えるために、日中はしっかりと活動させることも重要です。日中にたくさん遊び、適度な疲労感を感じることで、夜は自然と眠くなる傾向があります。また、日中の昼寝の時間や長さも調整し、夜の睡眠に影響が出ないようにすることがポイントです。
忍耐強く続ける
最後に、忍耐強く続けることが大切です。赤ちゃんの寝かしつけは、一朝一夕でうまくいくものではありません。毎晩のルーチンを根気よく続けることで、少しずつ赤ちゃんもそのリズムに慣れていきます。
結局のところ、赤ちゃんの寝かしつけは親にとって大きなチャレンジですが、適切な方法と忍耐強い姿勢を持つことで、少しずつ改善していくことができます。重要なのは、赤ちゃんが安心して眠れる環境を整え、親自身もリラックスして寝かしつけに臨むことです。
なぜ泣いてるのか?

赤ちゃんが泣く理由は様々で、親にとってはその原因を突き止めるのが一つの大きな課題です。なんとなく理由がわかるときもありますが、わからないときは一つずつ可能性を確認するしかありません。お腹が空いた、うんちやおしっこをした、寂しいから抱っこしてほしい、かまってほしい、暑い、寒い、眠い、体調が悪いなど、様々な理由が考えられます。
ある日のエピソード:突然の大泣き
ある日、私の赤ちゃんが突然大泣きを始めました。最初はお腹が空いたのかと思い、授乳を試みましたが、それでも泣き止みません。次に、おむつを確認すると、少し湿っていたので替えてみましたが、それでも泣き止まない。抱っこしてあやしても、部屋の温度を調整しても、赤ちゃんは泣き続けました。このように、泣いている理由がすぐにわからないことはよくあります。
お腹が空いた?
赤ちゃんが泣く最も一般的な理由の一つは、お腹が空いていることです。特に新生児は頻繁に授乳が必要です。泣き始めたら、まずは授乳を試みるのが一つの方法です。私の場合も、泣き始めてすぐに授乳を試みましたが、今回はそれが原因ではありませんでした。
おむつが濡れている?
次に考えられるのは、おむつが濡れていることです。赤ちゃんは湿ったおむつを嫌がりますし、不快感を感じると泣きます。私もおむつを確認し、少し湿っていたので替えてみましたが、今回の原因はこれでもありませんでした。
抱っこしてほしい?
赤ちゃんは寂しさや不安を感じると泣きます。特に、親のぬくもりを感じることで安心することがあります。私も赤ちゃんを抱っこしてあやしましたが、それでも泣き止むことはありませんでした。抱っこが原因で泣き止む場合も多いですが、今回はそれが理由ではありませんでした。
暑い?寒い?
赤ちゃんは体温調節が未熟なので、暑さや寒さに敏感です。部屋の温度を調整し、赤ちゃんの体温を確認しましたが、特に問題はなさそうでした。適切な服装に変えても泣き止まない場合は、他の理由を考える必要があります。
眠い?
眠さが原因で赤ちゃんが泣くこともあります。赤ちゃんが眠そうにしている場合は、静かな環境を作り、寝かしつけを試みることが有効です。私もこの方法を試しましたが、今回はそれでも泣き止むことはありませんでした。
体調が悪い?
最終的に、赤ちゃんの体調が悪い可能性を考えました。発熱や風邪、その他の病気が原因で泣くこともあります。私も赤ちゃんの体温を測り、体調を確認しましたところ、いつもより体温が高いことがわかり、小児科に行くことになりました。
改めて抱っこしてみるといつもより体が熱いことがわかり、以降、子供が発熱していることは体を触るとすぐにわかるようになりました。
忍耐と観察が鍵
結局のところ、赤ちゃんが泣く理由を一つずつ確認し、忍耐強く対応することが大切です。泣いている赤ちゃんを前にして親が焦ることは多いですが、冷静に観察し、適切な対応を取ることで、少しずつ赤ちゃんが安心して泣き止むことができます。
病気・風邪

赤ちゃんの健康を守るためには、さまざまな注意が必要です。特に、親が気をつけるべき点は、赤ちゃんにとって重要なポイントです。
親が口にしたものを食べさせない
赤ちゃんに食べ物を与える際、親が口にしたものをそのまま与えることは避けるべきです。これは、虫歯菌を移してしまうリスクがあるためです。赤ちゃんの口腔内はまだ発達途上で、虫歯菌に対する抵抗力が弱いです。親が口にしたものを食べさせることで、知らず知らずのうちに虫歯菌を赤ちゃんに移してしまう可能性があります。
また親自身は体調が悪くなくても口腔内の風邪菌を移してしまい、赤ちゃんが熱を出すと言うケースもあります。
風邪のリスクを避ける
親が元気でも、赤ちゃんの免疫力はまだ弱いです。そのため、親が口にした食べ物を赤ちゃんに与えることで、風邪などの病気の原因となる菌やウイルスが移ってしまうことがあります。逆に、赤ちゃんが食べ残したものを親が食べて、翌日体調を崩すことがあれば、赤ちゃんから風邪をもらってしまっている可能性があります。赤ちゃんの健康を守るためにも、食べ物の取り扱いには細心の注意を払いましょう。
安易な抗生物質の使用を避ける
赤ちゃんが病気になったとき、安易に抗生物質を使うことは避けるべきです。抗生物質は腸内環境を乱し、後々のアレルギー体質の原因になることがあります。医師から抗生物質を処方されたときは、本当に必要なものであるかどうかをしっかり確認することが大切です。自己判断での服用はとても危険です。自己判断で服用しないと言うのはさらに危険です。適切な治療法を選ぶために、医師とのコミュニケーションを大切にしましう。
赤ちゃんの病気のサインに注意
赤ちゃんは言葉で症状を伝えることができないため、親が注意深く観察することが重要です。普段と違う泣き方や、食欲の低下、発熱、機嫌が悪いなどのサインを見逃さないようにしましょう。早期に異変に気づくことで、適切な対策を講じることができます。
健康的な生活習慣の確立
赤ちゃんの健康を維持するためには、規則正しい生活習慣を確立することが重要です。バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動を心掛けましょう。また、赤ちゃんの免疫力を高めるために、母乳育児を続けることも有効です。母乳には、赤ちゃんの免疫力をサポートする成分が含まれており、病気から守る役割を果たします。
予防接種の重要性
予防接種は、赤ちゃんを重篤な病気から守るために重要です。定期的な予防接種を受けることで、感染症のリスクを減らすことができます。予防接種のスケジュールを確認し、忘れずに受けるようにしましょう。また、予防接種に関する疑問や不安がある場合は、医師に相談することが大切です。
環境の整備
赤ちゃんが健康に過ごせる環境を整えることも重要です。室内の温度や湿度を適切に保ち、清潔を保つことで、病気のリスクを減らすことができます。また、赤ちゃんの遊び場や寝室には安全で清潔な環境を整えましょう。アレルゲンとなるホコリやカビを除去し、空気清浄機を使用することも効果的です。
親の健康管理
赤ちゃんの健康を守るためには、親自身の健康管理も欠かせません。親が風邪や感染症にかかると、赤ちゃんに移るリスクが高まります。手洗いやうがいを徹底し、体調管理をしっかり行いましょう。また、ストレスを溜めないようにし、適度な休息を取ることも大切です。
赤ちゃんの健康を守るためには、日常生活の中で多くの注意が必要です。食べ物の取り扱いや抗生物質の使用、健康的な生活習慣の確立など、さまざまな側面から赤ちゃんの健康をサポートしましょう。親自身も健康に気を配り、赤ちゃんと共に健やかな日々を過ごすことが目標です。
無料相談予約・お問合せ

SMSでお気軽にお問合せください
SMS/フォームでのお問合せ・ご相談は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。